新型コロナをきっかけに注目された「下水から感染症を探る」という新しい方法。アメリカではBiobot Analyticsという企業が、下水データとAIを組み合わせて感染拡大を予測し、全米規模のネットワークを作りました。一方、日本でも国立感染症研究所や大学による実証研究で成果が出ていますが、民間企業はなぜか参入していません。本記事では、その背景と日米の違いをわかりやすく解説します。
Biobot Analyticsと日本の取り組みを比べてみた
新型コロナの流行をきっかけに、世界中で「どうすればもっと早く感染拡大を見つけられるか」が大きな課題になりました。その中で注目されたのが 「下水を調べる」 という方法です。
ちょっと意外かもしれませんが、トイレや台所から流れる下水には、人の体から出たウイルスや細菌が含まれています。これを調べると、街全体の「健康状態」をまとめて把握できるのです。
アメリカでは Biobot Analytics(バイオボット・アナリティクス) という会社が、この下水データとAIを組み合わせて感染症を早期にキャッチする仕組みを作り、話題になっています。一方、日本でも似た研究が行われていますが、少し事情が違います。今回はその比較をわかりやすく紹介します。
Biobot Analyticsとは?
Biobot Analyticsは、アメリカのスタートアップ企業です。やっていることはシンプルで、
- 下水処理場やマンホールから水を少し採取する
- PCR検査でウイルスの遺伝子量を調べる
- AIで過去データや地域ごとの傾向を学習させ、流行の兆しを予測する
という流れです。
下水のデータは「病院に行かない人」「検査を受けない人」も含めて、地域住民全員の情報を反映します。そのため、感染が表に出る数日〜数週間前に兆候をつかめることが多いのです。
実際に、大学キャンパスでは「下水の数値が上がった数日後に感染者が急増」したり、病院では「事前に患者増を予測してベッドを確保できた」などの事例があります。さらに、アメリカ疾病対策センター(CDC)と組み、今では全米人口の約30%をカバーする下水監視ネットワークを担っています。
まさに「下水を街の体温計にする」役割を果たしているのです。
日本での取り組み
「下水で感染症を見つける」という発想は、日本でも古くからありました。例えば、ポリオの流行を監視するために下水を調べる方法は昔から使われています。
新型コロナでは、国立感染症研究所(NIID)、北海道大学、東京大学、大阪大学などが中心となって下水調査を実施しました。その結果、**「下水のウイルス量が増えると、数日後に患者数や入院数も増える」**ということが国内でも確認されています。
さらに、2021年の東京オリンピックでは、選手村の下水を毎日検査する仕組みが導入されました。そのおかげで、症状の出ていない感染者を早く発見できたと報告されています。
一部の自治体では、冬に流行するノロウイルスなどの監視にも下水を活用する動きが始まっています。
日本ではなぜ企業がやらないの?
ここまで読むと、「日本でもBiobotのような会社があってもよさそう」と思いますよね。ところが実際には、下水×AIの事業を展開する民間企業はほとんどありません。その理由はいくつかあります。
- 市場規模が小さい
日本は欧米ほど感染症対策に大きな予算を投じていません。企業から見て「ビジネスとして利益が出にくい」と判断されやすいのです。 - 行政主導の文化
公衆衛生は「国や自治体が担うもの」という考え方が強く、民間が自由に入り込む余地が少ないのが現状です。 - 社会的な受け入れの問題
「下水を調べて監視する」と聞くと、日本では「監視されている感」が強く出てしまいます。また、地域ごとに「感染が多い/少ない」と可視化することが差別や偏見につながるのでは、といった懸念もあります。
こうした理由から、日本では研究者と行政が中心、アメリカでは民間企業が主導という違いが生まれているのです。
日米の違いから見えること
Biobot Analyticsの成功は、技術力の差というより「仕組みと文化の違い」で説明できます。
- アメリカでは、スタートアップがリスクをとって先に動き、政府がそれを取り込む形で全国展開に。
- 日本では、国の研究所や大学が成果を出しても、それを社会実装するステップで止まりやすい。
つまり、日本にも技術はあるけれど、制度や受け入れ体制が課題なのです。
まとめ
下水を調べることで、感染症を早く見つけることができる。
アメリカのBiobot Analyticsはそれをビジネスとして広げ、国全体のシステムに組み込みました。
日本でも研究成果や実証は十分にありますが、事業化は進んでいません。
将来的には、感染症だけでなく、薬物使用の傾向や生活習慣病の広がりなど、さまざまな健康データを下水から得られるようになるかもしれません。
下水は「街の健康を映す鏡」。その可能性をどう社会に生かすかが、これからの課題と言えそうです。




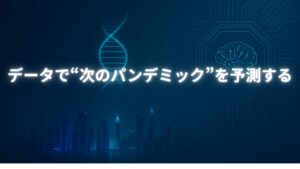




コメント